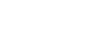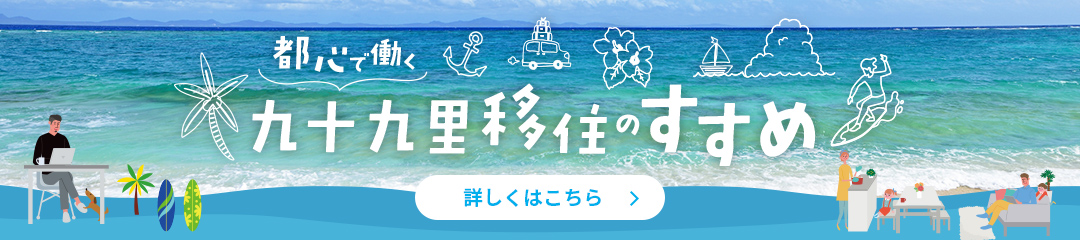家づくりのきっかけについて教えていただけますか?
ご主人: 犬を飼っているんですが、この近所にあるドックラン付きのホテルに泊まったことが家づくりのきっかけでした。
テラスに段差がなく、犬も外と中を自由に行き来きできる。
「こんなホテルのように、愛犬と気兼ねなく遊べて、快適に過ごせる住まいが建てられたらいいな」と思ったことからスタートしました。

九十九里地域でドッグラン付き物件を探していたんですが、妻のInstagramにエミグランデ(ドッグラン付きの賃貸物件)の広告が表示されて、「こんな物件があるんだ」と知りました。
当時は、別の場所で庭付きの一軒家を賃貸していましたが、草抜きやフェンス作りなどが大変でドッグランを自分達で作るのは「やっぱり難しいな」と思っていた時に、エミグランデの広告を見て「一度見てみたい!」と、思い動き出しました。
実際に、物件を見させていただき、住まいの発見館さんの想いや考え、家づくりのことを聞くと、コンセプトにとても共感し、「九十九里に移住したい」という思いが強まりました。
他の会社の物件も見ましたか?
ご主人: エミグランデに移るとき他の中古物件の情報なども見ましたが、結局、庭の草の問題などがありました。
引っ越した後は、特に他の物件を見ることはありませんでした。
奥様: なかなか良い物件が見つからず、インターネットで見つけた他の土地も見ましたが希望に合いませんでした。
そんな時にエミグランデの広告を見て、すぐに申し込みました。
ご主人: この家が建つまでエミグランデに長期間居住することができ、その間に、地域の人とも友達になり、ドッグランスペースを開放し合うなど、素晴らしい環境で過ごすことが出来ました。
住まいの発見館さんには感謝しています。
家づくりでこだわったポイントはどこでしょう?
ご主人: 僕は光が好きで、リビングや書斎など外の窓の大きさや場所にはこだわりました。
庭を眺めながら仕事をしたり、リビングでくつろぎながら外を感じれたり、できるだけ大きい窓をつけたいと思っていました。

奥様: 私は、間取りです。
自分で間取り図を書いたりしながら、「どんな家だと暮らしやすいか?」を想像して、何パターンもプランを作っていました。
書いたのを設計士さんに見せながら、意見をもらって進めて行きました。
リビングに両開きのドアを採用したり、玄関をR壁にしたり、家の中の仕上げ材や設備にもこだわり、どこか1つに絞りきれないくらいです。

引き渡し後の感想を教えてください。
ご主人: 皆さん「素敵な家ですね」とおっしゃっていただきます。
私たちも本当に満足しています。
家で過ごす時間は想像以上に快適です。
奥様:設計士さんや皆さんが非常に柔軟に対応してくれたおかげで、納得のいく家が完成しました。
住まいの発見館さんは本当に自由度が高く、我々の希望を最大限に尊重し夢を叶えてもらえました。
他の工務店さんやハウスメーカーさんと比較しても、これほど柔軟に対応してくれるところは少ないと思います。

ご主人: 我々のお願いに対して、常に最善を尽くしてくれる姿勢には感謝しています。
家づくりだけでなく、引き渡し後も家族のように接してくれるので、安心して長いお付き合いができると感じています。
私たちの希望を叶えるために親身に考えてくださり、本当にありがとうございました。